ミラノデザインウィークにて『Time & Style 2025 Collection』開催
注目の展覧会・イベント VOL.65
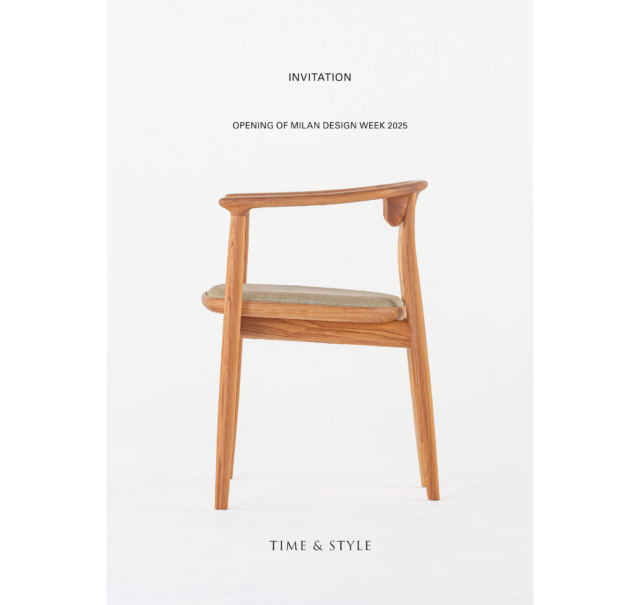
展覧会情報やインタビューなど、工芸に関するさまざま情報を発信しています。
2025.3.30 – 6.1
日本民藝館
2025.4.3 – 4.20
セイコーハウスホール
東京都
2025.4.5 – 4.13
courage de vivre
東京都
2025.4.5 – 6.22
静嘉堂文庫美術館

工芸品そのものは古くから存在するが、「工芸」という言葉が用いられるようになったのは、明治時代からとされている。それ以前は、機械生産される日用品というものはなく、すべては手作り品であり、手仕事そのものに特別な価値を見るということは少なかった。しかし明治時代になると、外国から「Fine arts」という言葉が伝わり、日本語としての「Fine arts」とは何かを考えるにあたり、絵画や彫刻などを「美術品」とし、それとは異なるものを「工芸品」と名づけることとなった。明治初期は、工芸という概念には工業品も含まれていたとされるが、機械生産が本格化するにつれ、「工業」という言葉も広く認知され、次第に工芸は美術や工業とは異なるものとして、独自の道を歩み始めたのである。
明治6年には、ウィーンで開催された万国博覧会に参加する際に、日本の魅力として紹介したものの中に伝統工芸があり、高い評価を得た。参加の目的の一つに、日本の国土の豊かさと伝統技術を海外に紹介することで、出展品の輸出を増やすことがあったとされ、伝統工芸品は、鑑賞目的のものから日用雑貨まで、幅広く出品された。
伝統工芸とは、「伝統性のある工芸」ということであり、その多くは地域の中で受け継がれている伝統技法や素材が用いられている。色や形のような意匠のことを指すのではなく、人の手による作り方が重要視され、有田焼や輪島塗、西陣織などのように、多くの工芸品はその名に地名が付けられている。例えば、日本の古い文様が描かれた一枚の青い絵のお皿があるとする。意匠だけであれば、伝統的な伊万里焼とも言いたくなるが、ただ青い絵の具で描かれただけでは伝統工芸と言うことはない。有田や九谷などに伝わる「染付」という伝統技法によって描かれていてこそ、伝統工芸なのである。
伝統工芸の中には、一子相伝を守り続け、その作り方が外部に漏らされていない技法も存在するが、一族で守り続けていくものだけでなく、産地全体で伝えていくことが多いのも、日本の伝統工芸の特徴であろう。輪島塗では分業制のもと、素材から塗りの技法まで、細かな作り方の指定があり、それを遵守しなければ、輪島塗とは認定されないことになっている。そうした伝統を重んじる文化は、イノベーションを阻害する面もあり、常に賛否両論あるものだが、グローバル化によってあらゆる国の都市が均質化していく中で、その地域にしかできないものづくりや美意識を追い求めていく姿勢は、新たな可能性を持ったものとして再評価される動きもある。
日本では、1974年に伝統文化の保護を目的として、経済産業大臣のもと「伝統的工芸品」というものが定められており、2024年10月時点で243点が指定されている。また、国とは別に県で定めているものもある。現代で伝統工芸と言えば、こうして国や県から認定を受けたものを指すことが一般的であり、伝統や地域にとらわれずに、異なる技法や素材を用いて作られているものは、カタカナでの「クラフト」や「現代アート」という言葉が用いられることが多い。
伝統工芸は、産業としては縮小の一途を辿っている。和食器や和服など、工芸品は日本の生活様式に合わせたものが多く、都市化していく暮らしの中で、需要が激減した。地方では人口減少により、職人不足も深刻なものとなっている。また、工芸は分業を基本とする産地が多く、さまざまな組合が存在する。組合は情報交換をしたり、素材の仕入れを工夫できるなど良い面もあるが、産地の慣習に縛られ、新たな取り組みが難しいという側面もある。商品価格も、地域の中であまり値段差をつけられないこともあり、職人の賃金が上がりにくい構造となっている。一方で、組合には所属せず、工芸作家として活動をする若者は少なくないが、個人作家の生産量には限りがあり、地域産業としての継続・発展には多くの課題が残されている。
工芸の歴史においては、美術工芸から民藝、そして生活工芸という流れが存在する。美術工芸とは、絵画や彫刻のような美術品を含めた文化財としての価値を持つものを意味し、日用品としての道具とは異なるものとされる。民藝は、昭和前半に柳宗悦が中心となって広めた文化活動である。当時、工芸と言えば観賞用の作品が評価され、個人の技法や表現を競い合うことで価値を高める傾向にあったが、柳宗悦らはそうした傾向に異を唱え、名のない職人が作る名のない雑器こそが、日本のものづくりの大きな魅力であり、そこに工芸としての価値があるのだとした。
そうした民藝の流れは現代にも受け継がれているが、その枝葉のなかで「生活工芸」というものが生まれた。生活工芸は、日常の暮らしそのものの美しさを重視し、生活に溶け込む工芸の魅力を再興させようとしたものだ。民藝は作家の作品ではなく、産地の分業制に基づく職人による生産品を重視したが、生活工芸は作家と職人を区別することなく、暮らしを豊かにしてくれる生活道具全般を大切にしている。現在、日本に多数存在する「うつわ屋」というのも、ここに該当するものが多い。うつわ屋とは、店主の好む作家が作る日常使いの食器を中心に販売するお店であるが、店主が作り手の生活や暮らし方に共感している点に特徴があり、伝統技法や習慣にとらわれない現代ならではの柔軟な思想と言える。
伝統工芸は、日本だけにあるものではなく世界各地に存在するが、陶磁器や漆器、金工に木工など、これだけ多種多様な伝統工芸が存在する国は希少である。日本の伝統工芸は、中国や朝鮮から伝わったものも多いが、日本の多様な風土や四季の存在、人々の手の器用さなどを強みとして、日本独自の発展を続けてきた。
伝統とは、長く続くためには、いつの時代にも必要とされていなければならない。しかしながら、ありとあらゆるものを変化させ続けてしまえば、文化としての魅力は失われてしまう。普遍的な価値を大切にしながらも、そのときの時代性を取り入れる柔軟さが求められる。そのためには、作り手は広い世界を見なければならず、伝統とはどうあるべきか、そしてその伝統とともに暮らすとはどういうことかを考え続けねばならない。
伝統的な物が存在しない世界を想像してみてほしい。何一つこれまでの足跡がない世界では、物事は消費されていく一方になる。私たちの人生は、一人一人にとっては一つの人生しかないが、伝統的な歴史の中には一つの足跡として確かに残っていくものがある。伝統工芸品をそんな視点から眺めてみてほしい。きっと、今の暮らし方に変化が生まれるはずだ。
参考:伝統的工芸品産業振興協会
https://kyokai.kougeihin.jp/